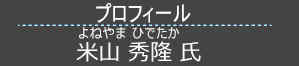新型コロナ禍で東京集中は終焉?
東京都の人口移動は、高度成長期には転入超過であったが、その後は長く転出超過が続いていた。その間も東京圏全体(1都3県)では転入超過だった。これは埼玉・千葉・神奈川の3県が転入超過だったことによる。東京都だけは「ドーナツ化」の進展で転出超過となっていた。
東京都の転出超過に歯止めがかかったのは1997年である。バブル崩壊後の地価下落、それに伴う大規模マンション開発により都心回帰が進んだためである。その後、転入超過数は増加を続け、リーマンショック時には縮小したが、アベノミクスによる景気拡大時は増勢が増した。
しかし、新型コロナ禍がこうした東京集中の流れに変化をもたらした。2020年の東京都の転入超過数は3万1,125人で前年比5万1,857人減少した。テレワークの普及が東京都からの転出を促したと考えられる。
ただ、転出先の過半数を埼玉・千葉・神奈川が占める。テレワークができても週数回で、残りの日は出勤が必要な人が多いため、移り住むにしても通勤との両立を図れる郊外にとどまっているとみられる。また、東京都では都心部の人口は2020年も増加した。職住近接により通勤時の感染リスクを減らせる点は、むしろ都心部の魅力を高めている。今後も地方への本格的な人口移動に至るとまでは考えにくく、新型コロナ禍が東京集中にストップをかけるとまではいえないのではないだろうか。
2021年3月29日
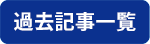
- トランプ政権の保護主義
(2018年4月2日) - 第4次産業革命、日本の可能性
(2018年4月9日) - “過度の悲観論”から脱却を
(2018年4月16日) - インバウンド
(2018年4月23日) - 初任給の底上げと格差
(2018年5月1日) - 「高圧経済」の功罪
(2018年5月7日) - デジタル・トランスフォーメーション
(2018年5月14日) - 景気の読み方
(2018年5月21日) - 明治150年に学ぶ“日本の底力”
(2018年5月28日) - 民泊新法
(2018年6月4日) - 先細る太陽光発電
(2018年6月11日) - 景気拡大の持続性
(2018年6月18日) - 米国の主張する「FFR」
(2018年6月25日) - イスラエルにて
(2018年7月2日) - 危機を乗り越え強くなった日本企業
(2018年7月9日) - 外国人労働者
(2018年7月17日) - 進まぬ老朽水道管の更新
(2018年7月23日) - 空き家ビジネス
(2018年7月30日) - ステルス・テーパリング
(2018年8月6日) - 新しい働き方
(2018年8月20日) - 観光で広がる経済成長の裾野
(2018年8月27日) - 廃校利用
(2018年9月3日) - 広がるシェアリングエコノミー
(2018年9月10日) - タワーマンションの今後
(2018年9月18日) - ベンチャー企業の「出口」
(2018年9月25日) - 地方創生はできるのか?
(2018年10月1日) - 外国人の視点に立った対応
(2018年10月9日) - ご当地ナンバー
(2018年10月15日) - なぜ、ユニコーン企業が出ないのか?
(2018年10月22日) - キャッシュレスによる地域活性化
(2018年10月29日) - 消費税の意義を考える
(2018年11月5日) - 「大いなる安定」の終わり
(2018年11月12日) - 貿易戦争でも景気拡大が続く米国
(2018年11月19日) - 「圏域行政」は特効薬になるか
(2018年11月26日) - 先端分野の外国人材も不足
(2018年12月3日) - 景気拡大に黄信号
(2018年12月10日) - 外国人労働のブレーキとアクセル
(2018年12月17日) - スーパー・シティをつくろう
(2018年12月25日) - 改元の年・2019年の景気は?
(2019年1月7日) - オーバーツーリズム
(2019年1月15日) - 訪日客4,000万人のハードル
(2019年1月21日) - 残された政策手段
(2019年1月28日) - 経済統計の「裏切り」
(2019年2月4日) - ダボス会議の後で…
(2019年2月12日) - 真田幸村の生き残り戦略に学ぶ
(2019年2月18日) - 波乱含みの統一地方選
(2019年2月25日) - 上場企業の業績が急速に悪化
(2019年3月4日) - コンドラチェフの長波
(2019年3月11日) - 見直される「過剰サービス」
(2019年3月18日) - 中国経済の見方
(2019年3月25日) - 令和を日本経済復活元年に
(2019年4月8日) - 転機迎えたふるさと納税
(2019年4月22日) - 東証一部の3分の1が降格?
(2019年5月13日) - 定額制のビジネスモデル
(2019年5月27日) - 関税戦争
(2019年6月10日) - 消費税と逆進性
(2019年6月24日) - 化粧品、食品…新輸出産業続々
(2019年7月8日) - 防災情報を知る
(2019年7月22日) - 最低賃金と中小零細企業
(2019年8月5日) - 空き家を増えにくくする方法
(2019年8月26日) - 政冷経熱
(2019年9月9日) - サマーダボスに出席して
(2019年9月24日) - 復活する日本のモノづくり
(2019年10月7日) - 関係人口を増やせるか
(2019年10月21日) - 70歳まで働き75歳から年金?
(2019年11月5日) - 廃墟マンション問題
(2019年11月18日) - オリンピック後の景気
(2019年12月2日) - イノベーションと人間力
(2019年12月16日)
- 五輪イヤーの景気見通しは?
(2020年1月6日) - 出生数90万人割れ
(2020年1月20日) - 革新の基盤、「5G」商用化
(2020年2月3日) - タワーマンション規制
(2020年2月17日) - 長期停滞論と新型ウイルス
(2020年3月2日) - 「コロナウイルス危機」に思う
(2020年3月16日) - 有事にこそ実力が試される
(2020年3月30日) - 地方公共交通の再構築
(2020年4月13日) - 中小事業者向け現金給付の課題
(2020年4月27日) - コロナ禍とデジタル化の進展
(2020年5月18日) - コロナがもたらした恩恵
(2020年6月1日) - アメリカの失業と日本の休業
(2020年6月15日) - アフターコロナのカギは「DX」
(2020年6月29日) - 観光立国の再出発
(2020年7月13日) - 都心居住人気の行方は?
(2020年7月27日) - 非合理を前提にした行動経済学
(2020年8月17日) - コロナ対策の副作用
(2020年8月31日) - 日本を変えた「アベノミクス」
(2020年9月14日) - 東京圏、初の転出超過
(2020年9月28日) - テレワーク人材獲得競争の激化
(2020年10月12日) - 急がれる日本のデジタル化
(2020年10月26日) - 産業再生への道
(2020年11月9日) - 上杉鷹山に学び危機突破を!
(2020年11月24日) - 新型コロナ感染拡大と医療体制
(2020年12月7日) - 「橋」が受難の時代に
(2020年12月21日)
- 問われる「オフィス」の意味
(2021年1月4日) - サブスクリプションの拡大
(2021年1月18日) - 新型コロナ問題の重要な視点
(2021年2月1日) - 渋沢栄一が我々に残したもの
(2021年2月15日) - 日経平均3万円乗せの虚実
(2021年3月1日) - 新型コロナ禍と都市の盛衰
(2021年3月15日)
1963年生まれ。
野村総合研究所、富士総合研究所、富士通総研などを経て2020年9月から現職。専門は住宅・土地政策、日本経済。主な著書に、『捨てられる土地と家』(ウェッジ)、『縮小まちづくり』(時事通信社)、『限界マンション』(日本経済新聞出版社)など。
【米山秀隆オフィシャルサイト】